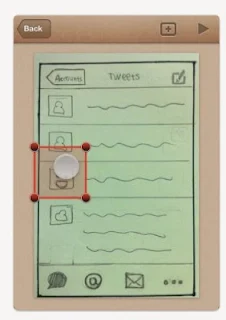WEBで仕事をする上で多少なりとも知っておいたほうが良い知識がJavascriptですよね。
WEBの解析などでもソースを見てなんとなく読める程度の知識は欲しいところですが、この本はサンプルとして90行のコードを紹介し、そのひとつひとつの文の解説で書き方と何が行われているかを紹介、そして文章全体の組み立て方、考え方などひと通りを学ぶことができます。
最後はjQueryの基本と、HTMLの基本、CSSの基本的な部分が書かれています。
Javascriptの本を手に取るということはHTML、CSSの知識は問題無いとおもいますが、jQueryは知っておきたいですよね。
私自身はjQueryの知識が無いので新鮮でしたが。
javascript自体の知識は少しだけしかありませんが、今回この本を買った理由としてはjavascriptの基礎知識があれば、もう少し活用出来るようになりそうなGoogle Apps Script、所謂GASのScript組立の知識としても役立つかなと思ったからです。
もちろんWEBで使うjavascriptとGASは全く別物ですが、同じくfunctionで関数を定義したりvarで変数を定義したり、似た部分も多いんじゃないかと素人ながら感じています。
javascriptを学ぶことで一石二鳥な気がしています。
そんな気持ちで手にとった本ですが、にわかの知識だけだったjavascriptの強化とjQueryを少しかじれて、とても良い本だと思います。
わかりやすい本なので、これから知識を付けたいという人の入門書としては最適ですよ。

 ノンプログラマのためのJavaScriptはじめの一歩 (WEB+DB PRESS plus)
ノンプログラマのためのJavaScriptはじめの一歩 (WEB+DB PRESS plus)
WEBの解析などでもソースを見てなんとなく読める程度の知識は欲しいところですが、この本はサンプルとして90行のコードを紹介し、そのひとつひとつの文の解説で書き方と何が行われているかを紹介、そして文章全体の組み立て方、考え方などひと通りを学ぶことができます。
最後はjQueryの基本と、HTMLの基本、CSSの基本的な部分が書かれています。
Javascriptの本を手に取るということはHTML、CSSの知識は問題無いとおもいますが、jQueryは知っておきたいですよね。
私自身はjQueryの知識が無いので新鮮でしたが。
javascript自体の知識は少しだけしかありませんが、今回この本を買った理由としてはjavascriptの基礎知識があれば、もう少し活用出来るようになりそうなGoogle Apps Script、所謂GASのScript組立の知識としても役立つかなと思ったからです。
もちろんWEBで使うjavascriptとGASは全く別物ですが、同じくfunctionで関数を定義したりvarで変数を定義したり、似た部分も多いんじゃないかと素人ながら感じています。
javascriptを学ぶことで一石二鳥な気がしています。
そんな気持ちで手にとった本ですが、にわかの知識だけだったjavascriptの強化とjQueryを少しかじれて、とても良い本だと思います。
わかりやすい本なので、これから知識を付けたいという人の入門書としては最適ですよ。